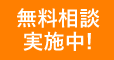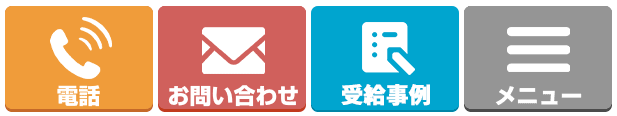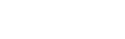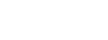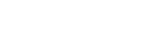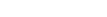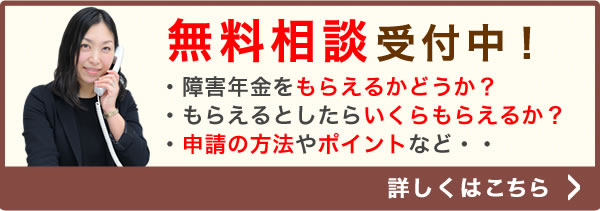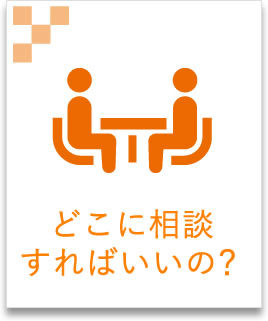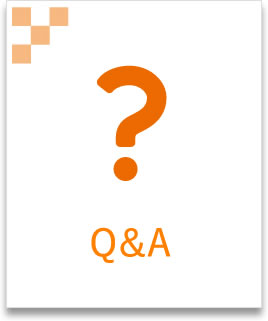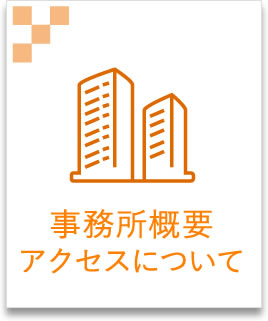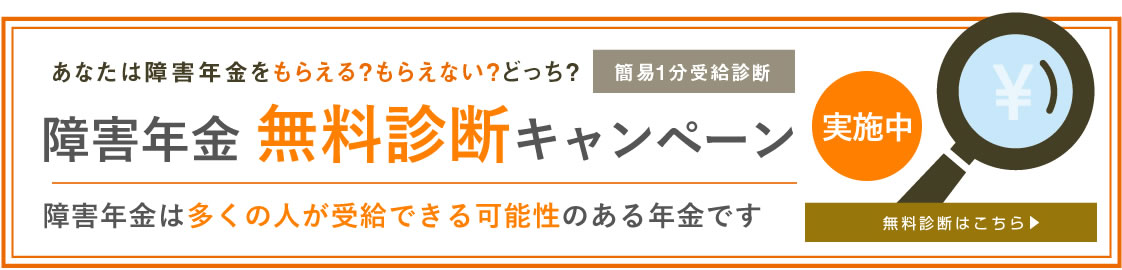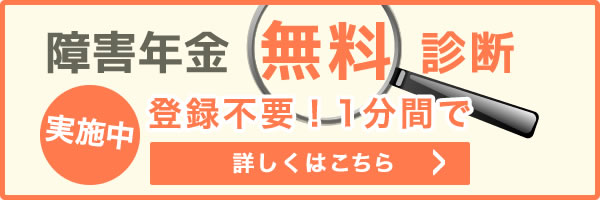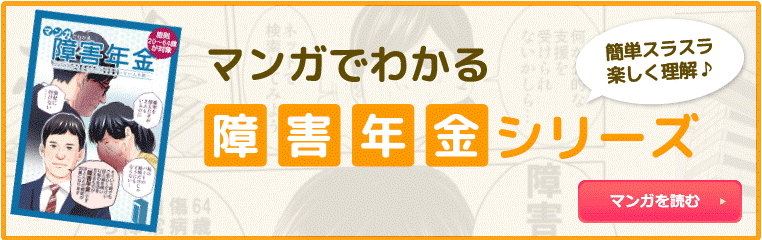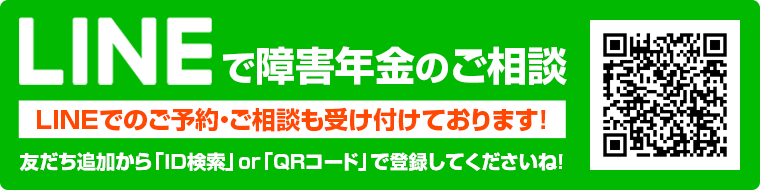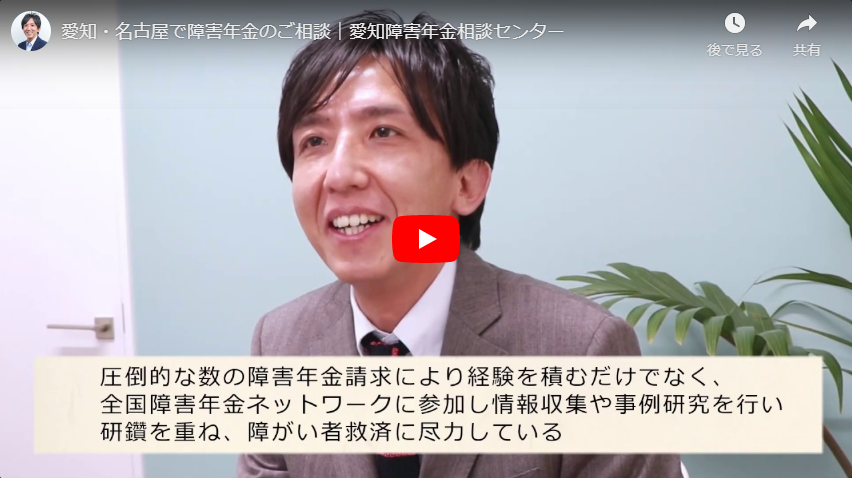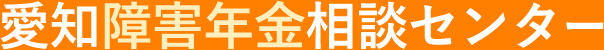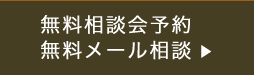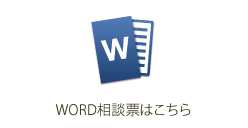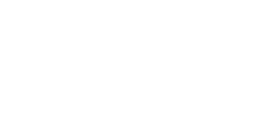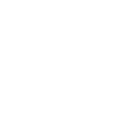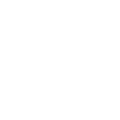人工血管・ステントグラフトの挿入されている方は障害年金の対象です
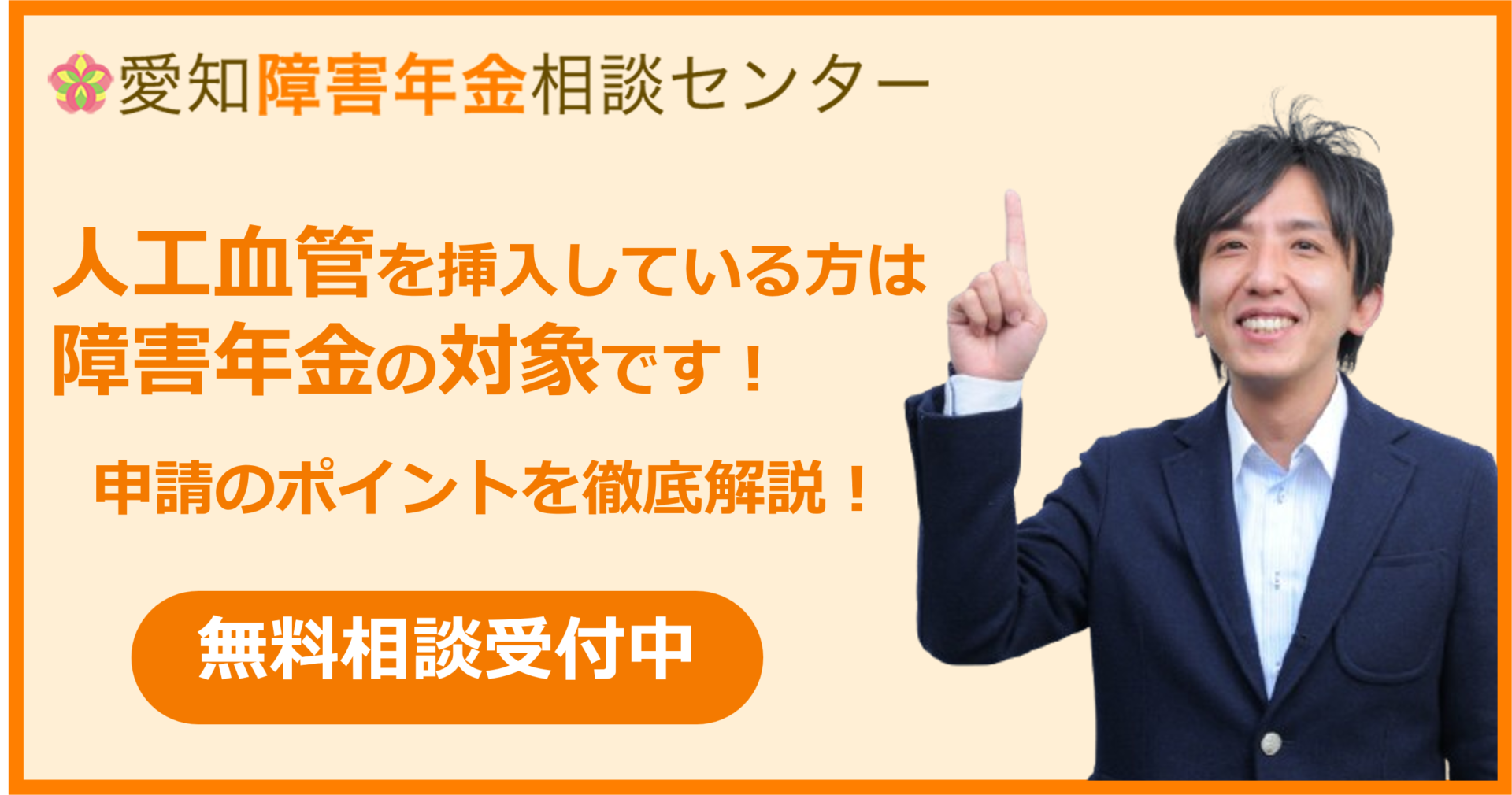
「大動脈瘤や大動脈解離などの治療で、人工血管(ステントグラフト)を挿入する手術を受けたけれど、以前のように働けなくなった…」 「手術後も体調が不安定で、日常生活に支障が出ている…」
このようなお悩みを抱え、経済的な不安を感じている方はいらっしゃいませんか? 人工血管(ステントグラフト)の手術を受け、一定の条件を満たす場合、障害年金を受給できる可能性があります。
しかし、「人工血管を入れたら必ずもらえるの?」「どんな状態なら対象になるの?」「手続きが複雑そうで不安…」といった疑問も多いかと思います。
この記事では、障害年金申請の専門家である社会保険労務士が、人工血管(ステントグラフト)に関連する障害年金の認定基準や申請のポイント、注意点について分かりやすく解説します。
そもそも障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方に対して、国から支給される公的な年金です。原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に加入していた年金制度によって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業、フリーランス、無職の方、専業主婦(夫)、学生など)が対象。障害等級は1級と2級があります。
障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象。障害等級は1級、2級、3級があり、さらに軽度の場合は一時金として「障害手当金」が支給されることもあります。
人工血管(ステントグラフト)=障害年金受給ではない!重要なのは「状態」
ここで最も重要な点をお伝えします。それは、「人工血管(ステントグラフト)を挿入したこと」自体が、直接的に障害年金の受給要件となるわけではないということです。
障害年金の審査で重視されるのは、以下の点です。
①原因となった傷病: 人工血管(ステントグラフト)を挿入する原因となった大動脈瘤や大動脈解離などの傷病の状態。
②手術後の状態: 手術を受けた後の日常生活や労働能力への支障の程度。
つまり、人工血管(ステントグラフト)の手術を受けたという事実だけでなく、その結果として、どの程度生活や仕事に制限が生じているかが判断基準となります。
障害認定基準:「循環器系の障害」のポイント
人工血管(ステントグラフト)に関連する障害年金の認定は、日本年金機構が定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「第7節 循環器系の障害」に基づいて行われます。
審査では、主に以下の点が総合的に評価されます。
①自覚症状
動悸、息切れ、胸痛、むくみ、失神などの症状の有無や程度。
②他覚所見(検査結果)
心電図、心エコー、胸部X線、CT、MRI、血管造影検査などの検査結果。
人工血管(ステントグラフト)の留置状況、血流の状態、合併症の有無など。
③一般状態
日常生活(食事、入浴、着替え、移動など)や労働がどの程度制限されているか。これは「一般状態区分表(ア~オ)」という指標で評価されます。
(ア) 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
(イ) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (例:軽い家事、事務職など)
(ウ) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの (例:歩行は可能だが長時間は無理、週に数日・短時間なら就労可能など)
(エ) 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
(オ) 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
④治療の効果・経過
手術後の経過、治療内容、服薬状況、合併症(脳梗塞、腎不全など)の有無、再発・再手術のリスクなど。
障害等級の目安
3級(障害厚生年金のみ): 労働に著しい制限を受ける状態。一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当し、検査所見にも異常がある場合など。
2級: 日常生活に著しい制限を受ける状態。一般状態区分表の「ウ」または「エ」に該当し、検査所見にも異常がある場合など。
1級: 他人の介助がなければ日常生活がほとんどできない状態。一般状態区分表の「オ」に該当する場合など。
人工血管(ステントグラフト)を挿入していても、特に自覚症状がなく、日常生活や仕事に大きな支障がない場合は、障害年金の対象とならない可能性もあります。一方で、手術後も息切れや倦怠感が強く、長時間の労働や立ち仕事が難しい、日常生活でも介助が必要といった場合は、受給の可能性が高まります。
障害年金申請手続きのポイントと注意点
障害年金の申請は、必要書類が多く、手続きも複雑です。人工血管(ステントグラフト)の場合、特に以下の点に注意が必要です。
①初診日の確定と証明
人工血管(ステントグラフト)の原因となった傷病(大動脈瘤など)で、最初に医師の診療を受けた日が「初診日」です。
この初診日を特定し、「受診状況等証明書」などで証明する必要があります。カルテが破棄されている場合など、証明が難しいケースもあります。
②診断書(循環器系の障害用)
障害年金申請において最も重要な書類です。主治医に作成を依頼します。
現在の症状、検査所見、日常生活や労働能力への支障について、具体的に、実態に即して記載してもらうことが重要です。遠慮せずに、ご自身の状況を正確に医師に伝えましょう。
人工血管(ステントグラフト)を挿入している」という事実だけでなく、「その結果、どのような支障が出ているか」を詳しく書いてもらうことがポイントです。
③病歴・就労状況等申立書
発症から現在までの経過、受診歴、治療内容、日常生活や就労状況の変化などをご自身(またはご家族)が作成する書類です。
診断書を補完する重要な書類であり、発症時の状況、症状の変化、人工血管(ステントグラフト)手術の経緯、術後の生活状況、仕事での支障などを、時系列で具体的に、矛盾なく記載する必要があります。審査において重視されるため、丁寧に作成しましょう。
④その他必要書類
年金手帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など、状況に応じて必要な書類があります。
複雑な手続きは専門家(社労士)への相談がおすすめ
ここまで見てきたように、障害年金の申請は、認定基準の解釈や必要書類の準備、特に「病歴・就労状況等申立書」の作成など、専門的な知識と経験が求められる場面が多くあります。
「自分で申請してみたけれど、不支給になってしまった…」 「書類の書き方が分からない…」 「仕事や体調のことで、手続きを進めるのが難しい…」
このような場合は、障害年金申請の専門家である社会保険労務士(社労士)にご相談いただくことを強くお勧めします。
社労士に依頼するメリット
①受給可能性の的確な判断
専門家の視点から、受給の可能性があるか、どの等級に該当しそうかなどを判断します。
②煩雑な手続きの代行
書類収集や作成、年金事務所とのやり取りなどを代行し、申請者の負担を大幅に軽減します。
③認定基準を踏まえた書類作成サポート
特に「病歴・就労状況等申立書」について、障害認定基準やご本人の状況を踏まえ、審査で有利になるような具体的かつ適切な内容の作成をサポートします。
④医師との連携
診断書作成依頼時に、記載してほしいポイントなどを医師に的確に伝えるお手伝いをします。
⑤不服申し立て(審査請求・再審査請求)のサポート
万が一、不支給決定となった場合でも、その後の不服申し立て手続きをサポートします。
まずはご相談ください
人工血管(ステントグラフト)の手術を受け、その後の生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。しかし、そのためには、ご自身の状態が障害認定基準に該当することを、適切な書類を通じて具体的に示す必要があります。
申請手続きは複雑ですが、決してあきらめないでください。ご自身での申請が難しいと感じたら、ぜひ私たち障害年金専門の社労士にご相談ください。
当事務所では、無料相談を実施しております。障害年金に関する疑問や不安、手続きに関するお悩みなど、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。経験豊富な社労士が、あなたの状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。
最終更新日 2025年4月3日 by 社会保険労務士 久保将之
コラムの最新記事
- ペースメーカーを装着している方は障害年金の対象です!もらえる条件や等級基準・申請ポイントを解説
- 双極性障害で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説
- 統合失調症で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説
- 【障害年金】家族が脳梗塞になったら手続きをご検討ください
- 人工透析(慢性腎不全)は障害年金の対象です。条件・認定基準・申請方法を詳しく解説!
- 障害年金の遡及請求とは?認められやすい傷病と難しいケースを紹介!
- 傷病手当金の終了後や退職後は障害年金の申請をご検討ください
- うつ病など精神疾患は障害年金がもらえる可能性があります
- 働きながら精神疾患(うつ病)で障害年金はもらえる?障害者雇用とフルタイムでの違い
- 大人の発達障害は障害年金の対象です。ADHD・ASDでの受給事例を紹介!
- 人工関節挿入で障害年金をもらうために|金額や等級・受給事例を紹介!